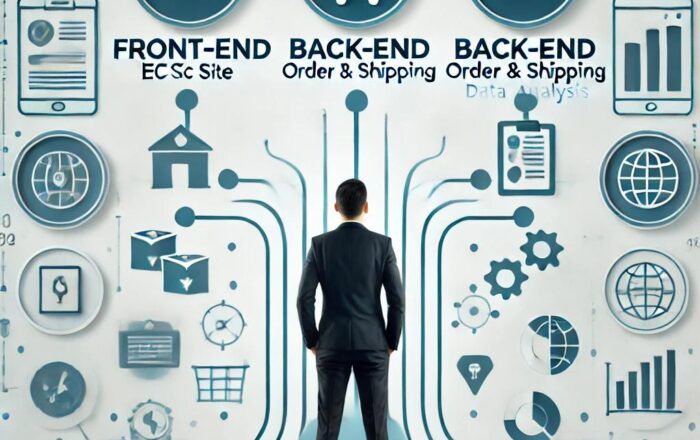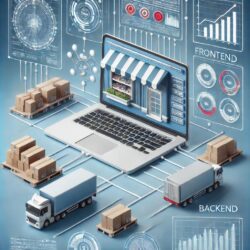通販業務に関するシステムは、世の中に多種多様なものが存在します。フロント部分のECサイトに組み込まれているもの、手軽に購入できるパッケージソフト、高価で大規模事業向けの基幹システムなど、その種類も価格帯も幅広いです。そのため、「いったいどれを使えばいいのかわからない」といったご相談をいただくことも少なくありません。
確かに、価格は数万円のものから数百万円に及ぶものまでさまざまですが、どのシステムも一見すると似たような機能を持っているため、違いが分かりにくいのが実情です。そこで、私がまずお勧めしたいのは、通販業務全体を以下の3つのパートに分けて考えることです。
① フロント部分:注文を受ける仕組み(例:ECサイト、モール、電話注文など) ② バックエンド部分:注文後の処理から出荷指示まで(例:受注管理、在庫管理、出荷指示など) ③ 分析・活用部分:蓄積されたデータを活かす仕組み(例:顧客分析、販売分析、販促施策など)
このように業務を整理して考えることで、自社に本当に必要な通販システムの構成が見えてきます。すべてを一体化したシステムは一見便利に見えますが、後々の拡張性や柔軟性に欠ける場合があり、注文チャネルを増やしたい場合や新たな分析機能を導入したい場合に対応が難しくなることがあります。
次に重要なポイントは「カスタマイズのしやすさ」です。通販業務は事業の成長とともに変化していきます。導入当初は必要なかった機能が、次のステージでは不可欠になることも多々あります。その際に柔軟にカスタマイズが可能であること、そして安心して相談できるパートナーがいることが非常に重要です。単に通販システムを販売する会社ではなく、通販業務の運営ノウハウを持ったサポート体制が整っているかも見極めるべきポイントです。
さらに、通販システムは一度導入すると業務に深く根付くため、簡単に切り替えることができなくなります。頻繁なシステム変更は、データの移行やスタッフの再教育といった手間だけでなく、現場にストレスを与えることにもなります。そのため、導入時には将来の拡張も見据えた柔軟なバックヤードの構築を目指すことが理想です。
また、通販システム導入の目的は業務効率化ですが、それによって得られた時間やリソースをどう活用するかも重要です。一元管理された情報を活用し、販促施策や顧客サービスの向上につなげるなど、新たなステージに向けた取り組みが求められます。ITの力をうまく活用することで、売上向上やリピート率の改善といった成果にもつながっていくのです。
このように、通販システムは導入して終わりではなく、その後の運用や成長に合わせて継続的に進化させていくものです。将来のステージを見据え、柔軟に対応できるシステムを選定することこそが、通販業務を安定して成長させていくための大切なステップなのです。